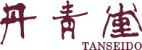墨について
普通の墨は膠と煤で造りますが、青墨は一般的には膠・煤の他に本藍などを入れてあります。このため、淡墨時(墨液を5~30倍程度に水で薄めたとき)の墨色が違います。青墨は水墨画等に用いる事が多く、作品に応じて墨色は使い分けるほうがいいでしょう。
漢字用でも質の良いものなら仮名用としてご使用いただけます。ただし、練習用の漢字用墨ですと濃墨にしたときに、墨液の粘り等により繊細な仮名の表現に適さないことがあります。
採煙の過程、採煙する油の種類が異なります。安価な墨は鉱物系(石油等)の油を燃焼させ煤を短時間で大量に採取します。高価な墨は植物油煙(菜種油・胡麻油等)を燃やし、長時間かけて採煙します。この手間暇の違いが値段の違いに表れています。
硯との相性もあるため一概には言えませんが、青墨はやや硬いようです。
墨の価格は品質と重量により概略決まるようです。
材料的には同じですが、墨液には磨った墨と同じ状態を維持していくために安定剤などが含まれています。
筆について
4号(穂径約1cm)くらいの兼毫筆(価格は2,000円~3,000円程度)のものをおすすめします。
穂先に残った糊気を完全に揉みほぐして取り除き、穂先を整えて下さい。
篆書(てんしょ)・隷書(れいしょ)体には鼬・馬毛等の剛毛または羊毛の短鋒を、楷書・行書体には兼毫(馬毛と羊毛)を、草書体には墨含みのよい羊毛が適しています。
大筆は使用後すぐに洗って下さい。小筆は反故にした紙の未使用部分に数滴水を滴らせ、穂先に残った墨を、穂先を整えながら水で濡れた反故紙に吸収させて下さい。
水洗いした大筆は穂首を下にして整え陰干しして乾燥させて下さい。また、買ったときに付いていた透明なキャップをかぶせると、湿気がこもることで毛の根元が腐り筆が傷みますので、二度と使用しないようにして下さい。
使用している原毛の質が異なります。高価な良い筆は厳選された細くて長く傷のない、若い弾力のある毛を選りすぐって使用しており、腰があって穂先がよく利く筆に仕上がっています。
細身でコシが強めの毛を使用している筆が適しています。
絵筆は動きが上下左右、どの向きに動かしても穂先が付いてくるような仕立てになっています。
日本画材について
日本画で使用する絵具には、大まかに天然岩絵具・新岩絵具・合成岩絵具・水干(すいひ)絵具・胡粉(ごふん)があります。また、その他にも鉄鉢(てっぱち)・顔彩(がんさい)・棒絵具・チューブ入り絵具などがあります。
天然岩絵具
天然自然に存在する鉱物(貴石)などを粉砕・精製した絵具で、代表的なものとしては藍銅鉱(らんどうこう)が天然群青の原料です。天然岩絵具の特徴のひとつに「焼く」(フライパンなどに入れて空炒りする要領で絵具を変色させる)ことが可能な点があげられます。また、天然のものなので、やや異なった色味の粒子も混ざっており、このために他の絵具には見られない深みがあります。
新岩絵具
天然岩絵具には色相が非常に限られているという欠点がありますが、これを補うのが新岩絵具です。ガラス体質(フリット)と金属酸化物を混合して、約800℃~1000℃程度で焼成・溶融して色の塊(人工の鉱物のようなもの)を造り、これを天然岩絵具と同様に粉砕・精製したものが新岩絵具となります。天然岩絵具とは異なり、焼いても色相は変化しません。
合成岩絵具
水晶や方解石を粉砕・精製してできた粒子を顔料や染料で着色した絵具で、特徴としては発色が非常に鮮やかということがあげられます。これは落ち着いた色味が多い天然岩絵具とは対極と言えるかもしれません。また、絵具の比重(体積当たりの重量)が同じなため、合成岩絵具同士であれば混色が簡単というのも特徴のひとつです。
水干絵具
顔料や染料に胡粉などを混ぜて、杉板の上で薄板状に自然乾燥させたもので、泥絵具とも呼ばれます。特徴としては非常に色数が豊富・粒子が細かくて塗りやすい・自由に混色ができる・安価などがあげられます。ただし、膠で練る前に乳鉢でよくすり潰す必要があります。
胡粉
天然の牡蠣(イタボガキ)の貝殻を屋外で放置(数年間)して風化させ、その後に粉砕・精製を行い杉板上で薄板状に自然乾燥させたものです。貝殻の身と蓋の両方が原料となりますが、蓋を使用した胡粉のほうが良質です。絵具として使用できるようにするまでに、乳鉢ですり潰す・膠で練った後に絵皿や乳鉢に叩きつけて空気を抜く・熱湯をかけてアクを抜く、などの手間が必要となります。
朱も他の絵具と同様に膠で練りますが、膠になじみにくい性質をもつので、一度に大量の膠を入れると練るのが困難となります(膠の上に朱が浮く)。
少量の濃い膠を入れて朱を潰すように練り、再び膠を入れるという手順をおすすめします。
日本画には削用(さくよう)・則妙(そくみょう)・隈取(くまどり)・附立(つけたて・付立)・連筆(れんぴつ)等の種類があります。
削用
主に直線や抑揚を抑えた線など、硬い感じの線を描く場合に使用します。穂先が利く筆です。
則妙
主に動物の毛や髪の毛など、軟らかい感じの線を描く場合に使用します。絵手紙の場合は、通常の線描きにも使用します。
隈取
ぼかしをする場合に使用します。水を含ませた状態で、ぼかしたい個所をなぞります。絵手紙の場合は、彩色にも使用します。
附立
骨(こつ・輪郭線)を描かずに対象を表現する場合に使用します。附立(付立)法というときは骨を用いずに対象を表現する技法をさし、没骨(もっこつ)法とも言われます。
連筆
幅広い面積を塗るために使用します。また、ぼかしや彩色にも使用します。
掛軸に仕立てる作品を制作する場合は、ある程度薄い紙に描かないと仕立てた際に巻けなくなります。また、膠が強過ぎたり厚塗りし過ぎた場合にもやはり巻けなくなるので、注意が必要です。
岩絵具は色相が限られており、必ずしも自分の出したい色がない場合があります。その場合に混色を行うことがありますが、色によって比重が異なるために、練ったときと同じ色になるとは限りません。色を置く作業と練る作業を並行して行う、または薄く数回に分けて塗ることでも、比較的望みどおりの色が出しやすくなります。
その他
軟らかく割れにくい(粘りがある)青田石(せいでんせき)がおすすめです。
中国産は「輝緑凝灰岩」、日本産は「黒色粘板岩」というように石質が異なります。どちらの石質も墨を磨るには良い石です。
表面の画仙紙が日本の画仙紙(和画仙紙)か中国の画仙紙(本画仙紙)かの違いです。にじみの強弱や墨色の出方などが違ってきます。
「人日(じんじつ)の節句」、「上巳(じょうし)の節句」、「端午(たんご)の節句」、「七夕(たなばた)の節句」、「重陽(ちょうよう)の節句」のことです。
皆さまからのご質問を承っております。
商品に関することや気になっていること、素朴な疑問まで、ご遠慮なくお尋ねください。