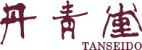古梅園と言えば墨。
墨と言えば古梅園。
書道や絵手紙などに欠かせない墨。
実は、その90%以上が奈良県でつくられた「奈良墨」なのを、ご存知でしょうか。
奈良県奈良市で生産されている墨を「奈良墨」と呼び、日本国内における固形墨のほとんどが奈良墨とされ、国内シェアは90%以上を占めています。
なかでも有名なのは、1577(天正5)年の創業から400年以上続く、日本最古の墨製造メーカー「古梅園」。
古都・奈良で墨づくり一筋、全国でも「煤採り」と呼ばれる手法から墨を製造しているのは古梅園だけという、長年培ってきた技術と昔ながらの製法を守り続ける唯一無二の存在です。
丹青堂でも非常に人気の高い「古梅園」の墨ですが、縁あって古梅園を訪問させていただくことができたので、その概要をご紹介します。
古梅園訪問記の目次
古梅園への道
古梅園があるのは、奈良県奈良市の椿井町。
丹青堂本店のある難波から近鉄奈良線を利用して奈良駅に到着、奈良駅に降り立った。
あらかじめ地図は用意しておいたものの、念のため駅近くの交番で道を尋ねることに。
「古梅園に行きたいのですが…」と尋ねると、すぐに答えが返ってきた。
こんなところからも古梅園の知名度の高さが感じられた。
暖かな日差しを受けつつ教えられた道を歩いていく。
道の両脇は商店街で、そこをまっすぐ行けば辿り着くはずである。
もともと少し静かであった道が先に進むにつれていよいよ閑静となり、右手に古めかしい建物が見えた。
建物にはやはり古めかしく、しかし確かに威厳を感じさせる看板があり、そこには古梅園の三文字が記されていた。
古梅園に到着したのである。
古梅園内へ

古梅園に入ると、右側に直売コーナー、左側に事務所、中央に「古梅園」と書かれた暖簾がある。
ひとまず挨拶をするために事務所へ。
営業氏と少し話しをした後、今回の訪問目的であるにぎり墨の自作体験と、天正年間から続く古梅園の墨造りを見学させてもらうために、暖簾をくぐらせていただいた。
古梅園の墨造り
採煙

最初に案内していただいたのは、墨の原料となる煤を採取するための工程である「採煙」を行っている採煙蔵(さいえんぐら)だった。
中は想像していたよりも狭く、また油を燃焼させているために、外よりも明らかに温度が高い。
ここで煤を採取するために原料となる菜種油なり胡麻油なり椿油なりを土器に溜め、そこに挿してある灯芯(いぐさを素材とした芯)の先端に火がともされる。
火が燃えるときに煤煙が発生し、これが上部に設置してある土器に付着するのだが、この付着した煤が墨の黒さの元となるものである。
十分に付着した煤を採取すれば採煙は一応完了となるわけだが、実際にはこれほど簡単にはいかない。

なぜなら、灯芯に火をともしたら煤が溜まるまで放置しているわけではなく、上部の土器に満遍なく付着させるために15分ごとに土器を45度回転させるからである。
この行為には、1箇所が集中して熱せられることで発生する煤の変質を防止する役割もある。
という事は、実に2時間もの時間をかけて、1周360度回転させていることになる。
おまけに採煙蔵内の写真を見てもわかるとおり、並行して複数個の土器を回転させなければならない。
一つを回転させ終えたら別の土器を回転、となると、いかに手間がかかる作業なのかが容易に想像できる。
膠溶解と型入れ

次に案内していただいたのは、採煙で採取された煤に混ぜるための膠が入った二重釜である。
古梅園で使用している膠の原料は牛の皮で、牛の品種についても古梅園なりのこだわりがあるのかと疑問に思い担当氏に質問してみたところ、「黒毛和牛がいいとかホルスタインがいいとか、そういう事はない」との答えが返ってきた。

長時間湯煎して造られた膠の溶液はやはり動物の皮からできたもので、独特の匂いがあった。
こうしてできた膠の溶液に煤と香料を混ぜ合わせ、しかし、そう簡単にはじゅうぶん混ざるものでもない。
そこで、じゅうぶん練り上げる工程が必要であり、これもまた職人さんが一つ一つ手作業で行う。
光沢が出るまで練り上げると言い、職人さんの手もおのずと黒光りしてくる。
黒光りした手の汚れは石鹸で洗っても容易には落ちないそうで、このあたりにも一丁の墨を造る事の大変さが窺い知れる。

ちなみに煤と膠の混合比であるが、多少の誤差はあるものの、煤100に対し膠60と決まっている。
この混合比は和墨(日本の墨)の場合で、唐墨(中国の墨)では膠の占める割合が和墨よりも多く、このために和墨のほうが墨のおりが早い事の原因となっている。
さて、じゅうぶんに練り上がったところで、自然の梨の木でできた墨型に入れる工程に移る。

二丁型なら30グラム、十丁型なら150グラムというように、一丁型の墨の重量は15グラムと決まっているが、これはあくまでも完成した墨の重量であって、墨型に入れる時点での生墨は乾燥して軽くなる事を考慮し、約22グラムほどとなる。
墨型には墨の名前や図柄などが彫刻されており、墨型に入れることで生墨に墨の名前や図柄が与えられる。
その後、生墨は墨型より取り出され、職人さんの傍らにある箱に収められる。
灰乾燥と自然乾燥

墨型から出された状態の墨には多くの水分が含まれており、この水分を抜くために乾燥の工程が必要になる。
乾燥には灰乾燥と自然乾燥の2種類があり、先に灰乾燥が行われる。
灰乾燥は簡単にいうと灰の中に墨を埋めて、墨に含まれている水分を灰に吸わせるということになるが、採煙に劣らず工夫が凝らされている。
灰乾燥第1日目の灰は、それ自体が水分を多く含んでいるために、墨は恐らくそれほど乾燥しないと想像できる。
第2日目以降より徐々に徐々に水分の少ない灰へと交換していくが、なぜこのように手間と時間をかけて乾燥させるのか。
一気に乾燥できれば結構なことだが、それでは墨が割れてしまうのである。
それを回避するために、小型の墨でもおよそ1週間、大型になればなるほど更に時間をかけて灰乾燥を行う必要がある。
灰乾燥を終えた墨は、次に自然乾燥という工程に移る。
自然乾燥の方法としては、藁で編まれて天井から吊るされ、陰干しされる。
こちらも、小型の墨で約2週間、大型になればなるほど長期に渡って吊るされ、なかには3か月も吊るされる墨もあるとの事。
その後の工程
その後、古梅園の墨造りは磨きや彩色といった工程を経る事になるが、残念ながら今回はタイミングが合わず見学することはできなかった。
興味がおありの方は、古梅園のホームページ(http://www11.ocn.ne.jp/~kobaien/)で墨の製造工程のページを参照していただきたい。
それにしても、一丁の墨を造るのにどれほどの時間と手間がかかるものか。
想像してみると、ただただ職人さんに頭を下げるほかなくなる。
にぎり墨の自作体験
事前に申し込んでおけば古梅園ではにぎり墨の自作体験ができるので、勉強も兼ねて体験させてもらうことにした。
型入れを行っている職人さんから棒状の生墨を渡していただき、その名のごとく手で握るのがにぎり墨の作り方。
利き手の右手で軽く握り、親指は生墨の上部を押さえる。
最初は少し力み過ぎたらしく、「あまり力を入れないで」と指導された。
握った手を開くと、自分の手の跡がはっきり残っている。
ぴったりと掌に収まるのは、握った本人だけなのかもしれない。
乾燥前の生墨を手にしたのは初めてであったので匂いを嗅いでみたが、製品として販売されている墨より膠の匂いが強かった。
今回握った生墨は鹿の膠を使用したもので、古梅園では鹿の膠による初のにぎり墨とのことであった。
ただし、にぎり墨ではない製品としては、既に鹿の膠を使用したものがある。
この後、古梅園の墨造りでも触れたとおり、1か月程度の乾燥工程を経て完成となる。
どのような仕上がりになるのか、1か月後のお楽しみというわけだ。

後日、件のにぎり墨が手元に届いた。
桐箱入りで、蓋には御にぎり墨と書かれている。
蓋を取ってみると中には綿が詰められ、自分がにぎった墨が収められていた。
実際に手に取ってみると、やはり乾燥して縮んだ為か手にぴったりとはいかなくなっていたが、墨に付いた手の跡が紛れもなく自分の手である事はわかる。
また、指紋さえも残っているのは面白い。
使うのもいいのだが、せっかくなので記念にとっておく事にした。
古梅園では既製品としてのにぎり墨もあるのだが、機会があればご自分の手でにぎり墨を握ってみるのも一興ではないだろうか。
時期や地理的な問題もあるが、可能な方は是非とも体験してみることをお勧めする。
古梅園内を散策する

ひととおり墨造りを見学し終えてから古梅園内を散策してみた。
古梅園には梅の木が植えられた庭があるが、この庭は型入れ工程を行う場所にも面している。
一生懸命に仕事をする職人さんには気にする暇もないかもしれないが、なかなかに趣のある庭ではないだろうか。
ことに見学した日はよく晴れて暖かな初秋、散策しつつも軽く睡魔に襲われそうなほどに、ゆったりとした気分となった。

担当氏に誘われ古梅園内にある休憩所に行ってみたのだが、ここでは個人的に、扉のすぐ脇にある物体に目を引かれた。
肥松(こえまつ)の見本である。
この肥松、悠揚迫らざるというか、実に堂々と休憩所に鎮座している。
肥松のすぐ隣には
肥松
「松材」で樹脂の多い部分
「松煙」を造る材料です
との説明文が記されていた。

休憩所内には古梅園の歴史が書かれた年表もあり、それを読みつつ改めて古梅園の歴史の長さを実感させられた。
その年表の隣には、何気なくぶら下がる宮内省 御用墨調合所 古梅園松井元淳と記されたプレート。
肥松とプレート、この2つに挟まれながら古梅園の墨造りを記録したビデオを拝見させていただいた。
古梅園を辞する

にぎり墨の自作体験と、いにしえより伝わる古梅園の伝統の墨造りの見学、2つながらの目的を達成し散策も済ませ、いよいよ古梅園を辞する事となった。
今回の古梅園訪問を通じ、正直なところ知識として頭ではわかっていたが今ひとつ実感の湧かなかった墨造りの苦労と、それでも敢えて現代にまで続ける老舗・古梅園に、畏敬の念を抱かずにはいられない。

その念は古梅園という存在のみならず、伝統の墨造りを今に伝えるべく日々尽力されているすべての職人さんに対し、かつまた、そうした職人さんの手により生み出された墨そのものに対しても抱くものである。
これを読んだ方が古梅園の墨を一丁なりともお持ちなら、今すぐにでもその墨を手に取っていただけないものだろうか。
あなたがお持ちの墨は、400有余年に及ばんとする長き歴史に育まれた優れた伝統工芸品であり、そして、まごう事なき墨の中の墨であるのだから。
かの文豪・夏目漱石の句を紹介させていただき、古梅園訪問記を終わりにしたいと思う。
墨の香や 奈良の都の 古梅園
私は、古梅園を辞した。